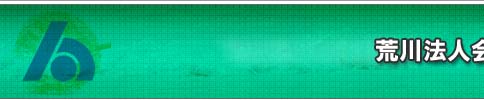| 法人税関係
■法人税率の引き下げ
法人税の税率が、現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。これにより法人実効税率は現行の34.62%から32.11%(東京に所在する法人の実効税率は35.64%から33.10%)になります。平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
■中小法人の軽減税率の特例の延長
中小法人の軽減税率の特例の適用期限が平成28年度末まで2年延長されます。
■商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者が経営改善設備を取得した場合に、取得価格の30%特別償却又は7%税額控除ができるもので、その適用期限が平成28年度末まで2年延長されます。
■欠損金の繰越控除制度の見直し
大法人(資本金1億円超の法人)の控除限度について現行の80%から次のとおり段階的に引き下げられます。なお、中小法人等については、従来通り控除限度額の制限は適用されません。
・平成27年4月1日から平成29年3月31日までに開始する事業年度65%
・平成29年4月1日以後開始する事業年度50%
また、繰越欠損金の繰越期間が現行の9年から10年に延長されます。平成29年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金から適用されます。
■受取配当金の益金不算入制度の見直し
保有割合の高い支配目的の株式の受取配当金については、100%益金不算入としつつ保有割合が現行の25%から1/3超に引き上げられます。
保有割合5%以下の株式は非支配目的の保有として、受取配当金の益金不算入割合が50%から20%に引き下げられます。
■所得拡大税制の見直し
雇用者給与等支給増加割合の要件について、中小企業者であれば平成28年4月1日以後開始する適用年度から5%以上が3%以上に、中小企業者以外は平成28年4月1日から平成29年3月31日までに開始する事業年度から5%以上が4%以上に緩和されます。
■外形標準課税の拡大
大法人の法人事業税のうち1/4に導入されている外形標準課税が2年間で1/2に拡大され、これにあわせて所得割の税率が引き下げられます。
平成27年4月1日以降開始事業年度と、平成28年4月1日以降開始事業年度と段階的に実施されます。
|